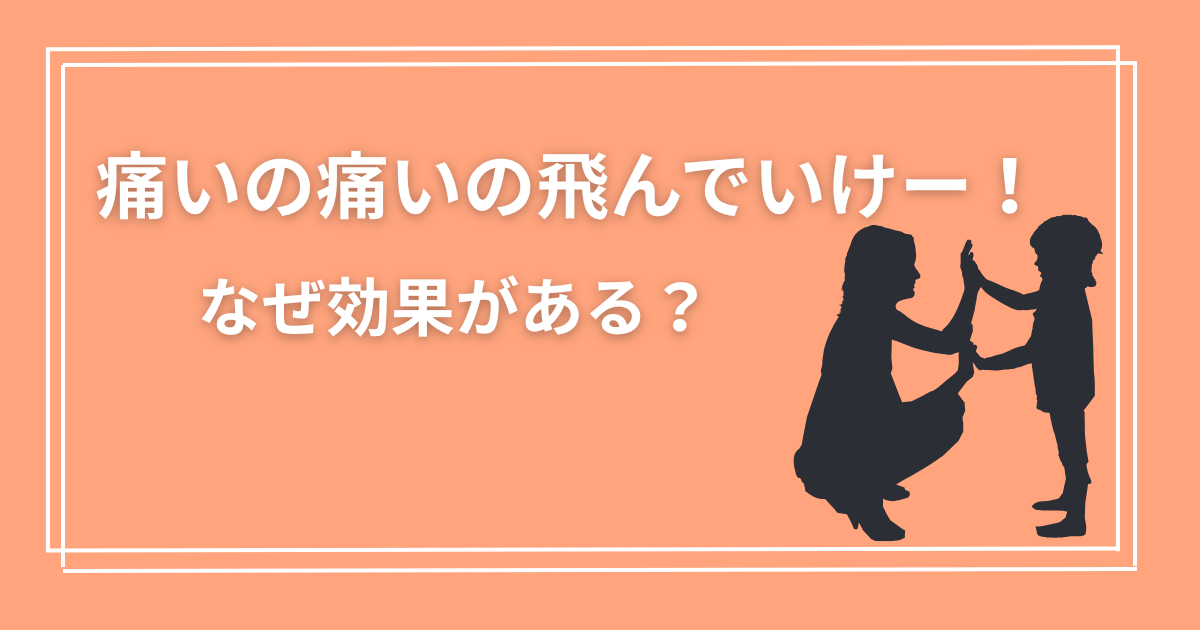「痛いの痛いの飛んでいけ!」――子どもの頃、身近な大人の人に言ってもらった記憶がある方も多いのではないでしょうか。
誰かが寄り添い痛みを和らげようとしてくれる。日常の一コマだけど、とても温かくて、世界中のすべての子にそうした誰かがいて欲しいと思います。
でも、実際、効果ってあるんでしょうか?
本当に効いた「痛いの痛いの飛んでいけ!」
うちの子どもが小さかった頃、「痛いの痛いの飛んでいけ!」をよくやっていました。
最初のうちはただ単に、痛いところに手をあてて唱えるだけだったんですが、どうやらかなり効果があるようなので、回を重ねるごとに真剣にいろいろと意識して行うようになりました。
どうも上達するようで、二人目の子にはさらに効果があり、それはもう魔法のレベルでした。
なぜ効くのか? 私なりの4つの理由
私が当時、自分なりに考えてみた「なぜ効くのか」の理由は以下のようなものでした。
- 精神的効果
誰かに施術してもらい寄り添われることで、言葉や身体的触れ合いから安心感が得られる。 - 患部に当てる手が引き起こす効果
本気でやっていると、患部と、数ミリ離れた自分の手の間にほんのり温かい空気が生まれることに気づいた。
これが「気」というものなのかな?と思った。
単に手が近くにあることで温度が上がるだけかもしれないが、何かそれ以上のもののような気がした。 - 声(音)の効果
心を込めて呪文(⁉)を唱えようとすると、声の高さや出し方を意識せずにはできなくなった。
話しかける時とは違った声の出し方だ。振動としての音が関係するのではないか。 - 潜在意識の力
そして何よりこれが一番関係があるのではないかと思うのは、受け手の潜在意識の力。
というのも、子どもがとても小さい頃とある程度物心がついてきてからとでは効果が違ったからだ。上の子も下の子も。
これは、子どもが本気で「痛さは飛んでいってしまう」と思っているか、知恵がついて「そんなことあるわけないよね」と思ってしまうかの違いなのではないかなと思う。
「痛いの痛いの飛んでいけ」の効果 科学的根拠
実際に科学的に効果が認められているという研究や応用できる理論があるのかどうか調べてみました。
1(精神的効果)は、乳幼児心理学の視点からアタッチメント効果による痛みの緩和として説明できるようです。
4(潜在意識の力)については、よく知られている暗示効果である「プラセボ効果」で説明できますね。
2(手が発するエネルギー)と3(音の力)については、私は強く推すものの、やはり予想通り科学的に証明するのは難しいようです。
そしてそれ以外に、しかも「痛いの痛いの飛んでいけ!」が効く最大の理由として多くの方が挙げているのは、「ゲートコントロール理論」というもの。
患部や周辺をさすったり押さえたりすると、痛み以外の感覚信号(触覚や温覚など)が先に脳に届いて痛覚神経に抑制がかかり、痛みの情報が脳に伝わることが抑えられるのだそうです。
私は初耳でしたが1965年に発表された学説だそうで、随分と古くから知られているのですね。
「痛いの痛いの飛んでいけ!」はやっぱり、心理的・生理的に効果があるようです。
今度机の角に足の指をぶつけた時には、痛いところを押さえたりさすったりしながら「とんでけ!」ってちっちゃい声で言ってみません?